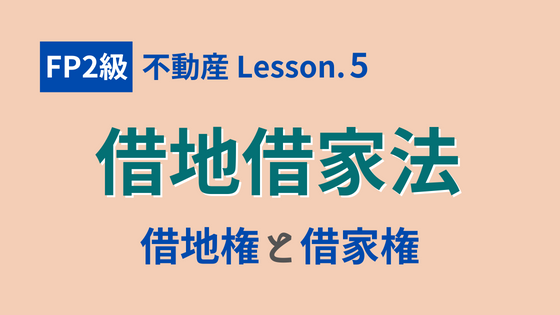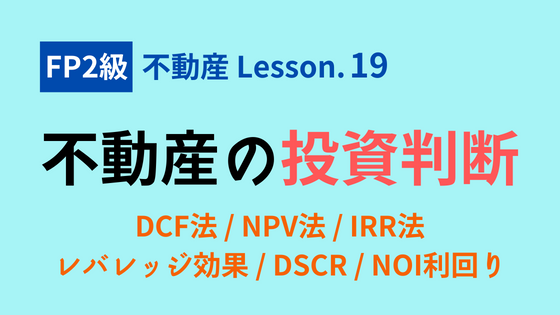【FP2級】農地法〜対象取引と市街化区域の特例


今回は”農地法”を解説します。農地の権利移動や転用をする際、どんな許可が必要になるかをおさえておきましょう。
- 農地の権利移動や転用の際に必要な許可を理解する
- 市街化区域の特例を理解する
※近年の過去問の傾向からは、農地法が出題される確率は低めです。ただし、農地法から1問出題されることもあるため、概要だけでも理解しておきましょう。時間がなければ飛ばして次回の“不動産取得時の税金”に進んでください。

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ
農地法の趣旨
農地法とは、日本の農業生産力を守るための法律です。
ただでさえ国土面積が少ない日本です。みんなが農地を自由に開発して農作物をつくらなくなれば、食料の安定供給が難しくなってしまいますよね。
それを防ぐため、農地の譲渡や転用を行おうとする人に、事前の許可を取ることを義務付けています。これが農地法の趣旨です。

農地法を理解するうえで、この趣旨は非常に重要です。
ここでいう農地とは、あくまで現況で判断され、不動産登記上の地目は関係しません。
登記上の地目は宅地になっていても、実際は畑として利用されていれば農地とみなされ規制対象になるということです。
不動産登記は案外テキトーなので、登記上の地目と現況が異なることはよくある話です。
この点はFP2級試験で問われることがあるので、しっかり理解しておきましょう。
農地法の対象取引
農地法において、許可が必要な取引は3つあります。
FP2級試験では問われるのは、それぞれ誰の許可が必要になるかです。
- 権利移動(農地法3条)・・・農業委員会の許可
- 転用(農地法4条)・・・都道府県知事の許可
- 転用目的での権利移動(農地法5条)・・・都道府県知事の許可

農業委員会ってなんだ?

農業委員会は農地利用の最適化を図るために、市町村に設置される機関です。あくまで市町村の機関なので、都道県知事の許可を取るよりハードルは低いです。
それぞれの取引について、詳しく見ていきましょう。
権利移動(農地法3条)
農地法3条により、農地の権利移動を行うときは農業委員会の許可が必要です。
権利移動で最も分かりやすいのが売買(所有権の移転)です。
売買以外には、賃借権や地上権、永小作権の権利を設定する場合も権利移動に該当し、農業委員会の許可が必要となります。
ただし、抵当権を設定するだけでは許可は不要なので注意しましょう。

無許可でやったらどうなるんだ?

無許可で権利移動を行なった場合、契約は無効になります。農地法はなかなか強力な法律なのです。
転用(農地法4条)
農地法4条により、農地を転用するときは都道府県知事の許可が必要となります。
“転用”とは、農地を農地以外にすることです。農地を宅地にして家を建てるイメージです。
都道府県知事の許可なので、農業委員会の許可よりもハードルが高いです。
その理由を考えるうえで、農地法の趣旨を思い出してみましょう。
農地法の趣旨は日本の農業生産力を守ることでしたね。先ほど学習した”権利移動”では持主がかわるだけで農地は減りませんが、今回の”転用”では農地自体が減ってしまいます。つまり、農地法の趣旨からするとより深刻な問題なわけです。
だからこそ”転用”には、しっかりと都道府県の知事を取ることを義務化しています。
転用目的での権利移動(農地法5条)
農地法5条により、農地を転用目的で権利移動する場合は都道府県知事の許可が必要です。
“転用目的の権利移動”とは、権利移動(3条)と転用(4条)をミックスしたものです。
たとえば、農地を不動産業者に売却(権利移動)し、その不動産業者がマンションを建築する(転用)といったケースが当てはまります。
転用を伴うため、もちろん厳しい方の都道府県知事の許可が必要となるわけです。
市街化区域の特例
ここまで学習した通り、”転用”や”転用目的での権利移動”を行う場合には都道府県知事の許可が必要となります。
しかし、都道府県知事の許可を取るのはそれなりに手間がかかります。
一方で、市街化区域は農地を守るというよりも、都市計画で市街化を進めていこうとする地域です。市街化区域では農地はむしろ宅地に転用してほしいわけです。
このため、市街化区域においては、手続を簡素化するための特例が設けられています。
事前の届出だけで済めば、手続きとしてはだいぶ楽になります。
注意すべきは、特例が認められるのはあくまで転用を伴う場合に限られることです。
権利移動だけでは、たとえ市街化区域内の取引であっても特例は認められず、農業委員会の許可が必要となります。権利移動は持主が変わるだけで、市街化には寄与しないからです。
農地法まとめ
最後にFP2級試験対策として農地法の要点をまとめておきます。
- 農地かどうかは、地目ではなく現況で判断される
- “権利移動”は農業委員会の許可が必要
- “転用”と”転用目的での権利移動”は都道府県知事の許可が必要
➡︎市街化区域では、事前に農業委員会に届出すれば許可不要

今回の学習はここまでです。農地法における許可や届出は理解できたでしょうか。次回は”不動産取得時の税金”を解説します。


試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ