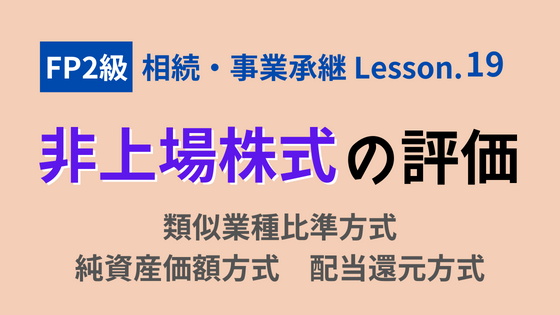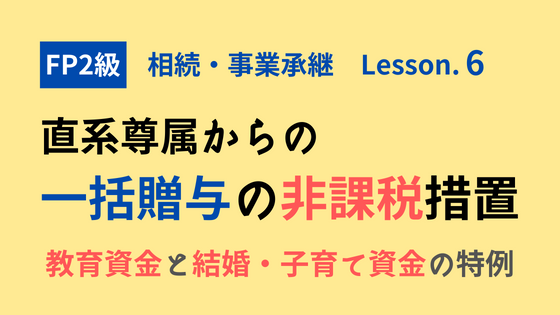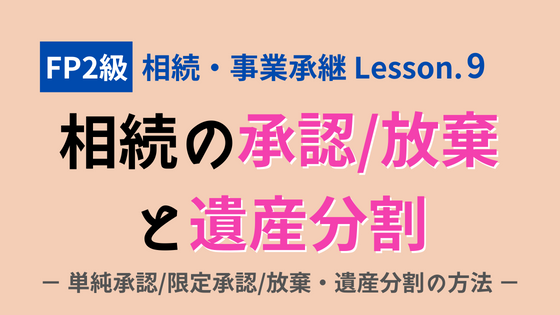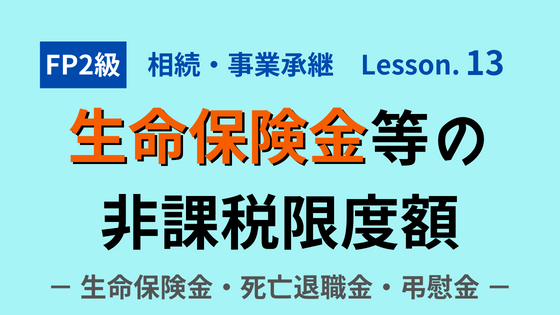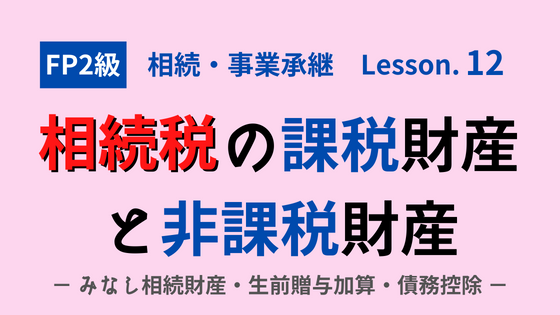【FP2級】遺言と遺留分〜遺言書の3類型と遺留分侵害額請求権


今回は遺言と遺留分について解説します。どちらもFP2級の定番ですが民法(相続法)の改正内容も合わせて押さえておきましょう!
- 遺言書の種類と特徴を理解する
- 遺留分と遺留分侵害額請求権を理解する

試験対策には“直前対策note(〜2026年5月試験対応)”がおすすめだぞ
遺言(いごん)
遺言とは
遺言とは、被相続人の最終の意思表示のことで、自身の死後における財産の処分などに影響を及ぼします。
前回の講義では、被相続人の遺言が存在する場合は、原則として遺言に基づき遺産分割を行うことを学習しましたね。
遺言は満15歳以上の意思能力を有する者であれば誰でも作成することができます。
15歳以上であれば、未成年者であっても親権者の同意は不要です。
遺言の学習に当たって、次の3つの言葉を覚えておきましょう。
| 遺贈者 | 遺言を行った者 |
| 受贈者 | 遺言により財産を取得する者 |
| 遺贈 | 遺言による財産の移転 |
遺言は一方的な意思表示で成り立つ単独行為なので、受贈者の承諾は不要です。

贈与は受贈者の承諾が必要な「諾成契約」でしたね。忘れてしまった人は「贈与の基本」で復習しておきましょう。
単独行為というくらいですから、たとえば夫婦共同の遺言書など、複数人で遺言書を作成することは認められていません。
一部の財産に限定した遺言も可能です。要するに、必ずしも全ての財産の受取人を指定する必要は無いということです。
また、遺言により相続分の指定を第三者に委託することも可能です。相続分の指定に迷う場合、弁護士などの専門家に任せるのもアリだということです。
遺言には次の3つの類型があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
FP2級ではこの3つの遺言書の違いを問う問題が頻出です。順番に学習していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身が日付・氏名・遺言書の内容を自署し、押印をする形態の遺言書です。
代筆は認められていませんが、印鑑は認印でもOK(つまり実印でなくてもOKということ)です。
遺言書の内容は自署が原則ですが、作成者の負担を軽減する観点から、2019年1月より財産目録だけは自書でなくてもOKということになりました。
財産目録とは、遺言書作成者の保有する財産の一覧表です。
パソコンでの作成はもちろん、通帳のコピーや登記簿謄本の添付で代用することも可能になりました。
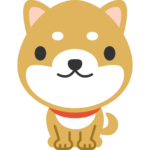
自署以外でも認められるのは、あくまで財産目録だけです。他は全て自署が必要だから注意しよう!
被相続人の自筆証書遺言を発見した被相続人は、開封することなく、速やかに家庭裁判所に提出して「検認」の手続を受けなくてはなりません。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するための証拠保全手続のことです。
自筆証書遺言は最も一般的な遺言書の形態です。
コストがかからず、最も手軽に作成できる点がメリットといえます。
一方で、次のようなデメリットも指摘されてきました。
こうしたデメリットを解消するために、民法(相続法)の改正により、2020年7月から法務局における“自筆証書遺言保管制度”が開始されました。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
この制度を利用することで、遺言書の偽造・変造が防げるほか、法務局に遺言書を保管している旨を推定相続人に伝えておけば、遺言書が発見されないリスクも回避できるというわけです。
偽造・変造の恐れがないことから、自筆証書遺言保管制度を使えば検認の手続きは不要となります。
手数料(収入印紙代)もこのあと学習する公正証書遺言に比べれば安価なので、今後利用が広がっていくかもしれません。

法改正は要チェックってやつだな
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場において遺言者が口頭で遺言内容を伝え、公証人がそれを筆記することで作成される遺言書です。
公証人は筆記した遺言書の内容を2名以上の証人に読み聞かせることで、内容の確認を取ります。
遺言書の原本は公証人役場に保管され、紛失や偽造・変造のリスクがないため、検認の手続は不要です。
最も確実に遺言を残す方法と言えますが、コストと手間がかかる点、公証人と証人には遺言の内容を知られてしまうという点がデメリットとなります。
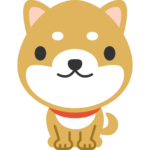
証人は2人以上であること、検認が不要であることを押さえておこう!
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、実務的にはあまり使われない方式ですが、FP2級では出題されることがあるのでしっかり押さえておきましょう。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を公証人役場に持ち込み、2名以上の証人の立会いのもと、公証人に遺言書の存在を証明してもらう方式の遺言です。
公証人役場では、遺言書の存在を確認してもらうだけで、公証人と証人は遺言書の内容を知ることはできません。
このため、公正証書遺言よりも秘匿性が高いといえます。遺言の内容を誰にも知られることなく、遺言書の存在を証明してもらえる点が秘密証書遺言のメリットと言えるでしょう。
遺言者の推定相続人等が証人になれない点は、公正証書遺言と同じです。
ただし、公正証書遺言とは異なり、遺言は法務局に保管されないため、遺言書の紛失や偽造・変造のリスクは回避できません。このため、検認の手続は必要となります。
3つの遺言の違い
3つの遺言の違いは以下の表で整理しておきましょう。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 筆記者 | 本人 | 公証人 | 本人が作成、公証人が日付を記入 |
| 証人 | 不要 | 2名以上 | 2名以上 |
| 検認 | 要* | 不要 | 要 |
遺言の撤回
遺言はいつでも、何度でも撤回することができます。
また、遺言の全部を撤回することも、一部のみ撤回することも可能です。
遺言の撤回は原則として遺言によってしなければなりません。
撤回する際は、当初の遺言と同じ形式ではなくても大丈夫です。
つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回してもOKだということです。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言が優先といったことはありません。
遺言書の種類に優劣はなく、日付の新しい遺言書が優先されるということを押さえておきましょう。
- 被相続人の死後、2022年1月10日付の公正証書遺言と2023年1月10日付の自筆証書遺言が発見されました。どちらの遺言に従うべきでしょう?
-
答えは「2023年1月10日付の自筆証書遺言」です。
遺言の種類に関係なく、後の遺言が優先されることを覚えておきましょう。

遺言書を捨てたらどうなるんだ?

その場合、破棄した部分については撤回したものとみなされるよ!
遺言まとめ
ここで遺言のポイントをまとめておきます。
- 自筆証書遺言は自署が原則、財産目録のみパソコン等での作成も可
- 自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認の手続が必要(自筆証書遺言保管制度を使った場合は検認不要)
- 公正証書遺言では、公証人が遺言の内容を筆記する
- 公正証書遺言と秘密証書遺言では、2人以上の証人が必要
- 推定相続人等は証人になれない
- 遺言の種類に関わらず、日付が新しい遺言が優先される
遺留分と遺留分侵害額請求権
遺留分(いりゅうぶん)とは
遺留分とは、遺言の内容に関係なく、相続人に最低限度の遺産の相続を保証する制度です。
たとえば、被相続人が全財産を愛人に相続させる旨の遺言をした場合を考えてみましょう。
遺言の通りに愛人が全財産を相続すると、残された遺族は生活に困窮してしまうかもしれません。
いくら被相続人の財産とはいえ、これではあんまりですよね。
こうした問題に対応するために、相続人のうち配偶者、子、直系尊属には、以下の通り遺留分が認められています。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属のみ | 相続財産の1/3 |
| それ以外* | 相続財産の1/2 |
表のとおり、相続人が父母などの直系尊属のみである場合、相続財産の1/3が遺留分となります。
たとえば、相続財産が6,000万円で相続人が母のみ場合、母の遺留分は2,000万円(6,000万円×1/3)なるということです。
それ以外の場合、つまり相続人に配偶者や子(代襲相続人を含む)が含まれる場合の遺留分は相続財産の1/2となります。
たとえば、相続財産が6,000万円で相続人が配偶者と子1人の場合、合計3,000万円(配偶者1,500万円+子1,500万円)が遺留分となるわけです。
なお、遺言では遺留分を侵害しないように考慮することが重要ですが、たとえ遺留分を侵害する内容であっても遺言書自体は有効です。
遺留分侵害額請求権
遺留分は黙っていても戻ってくるものではなく、遺留分権利者が主張してはじめて取り戻すことができます。
このように、遺族が侵害された遺留分に見合う金銭を請求できる権利のことを“遺留分侵害額請求権”といいます。
遺族は遺留分侵害額請求権を行使することで、受贈者から遺留分に見合う金銭を取り戻すことができます。
請求できるのは「金銭」なので、土地や建物といった現物資産の請求はできません。
また、遺留分侵害額請求権はあくまで権利であって義務ではないため、必要がなければ権利行使する必要はありません。
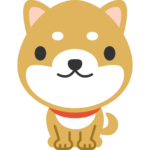
民法改正により、2019年7月から「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に名称が変更になりました。
遺留分の放棄と時効
遺留分は家庭裁判所の許可を受けることで、相続開始前に放棄することが可能です。
この点は相続の放棄とは異なるため注意が必要です。
また、遺留分には時効があり、いつまでも請求できるわけではありません。
以下のいずれかに該当したときは時効となり、以後は遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなります。
- 相続の開始を知った時から1年を経過したとき
- 相続の開始から10年を経過したとき
遺留分に関する民法の特例
少し難解ですが、ここからは“遺留分に関する民法の特例”の解説をします。
被相続人が中小企業の経営者であった場合、相続財産の大半が当該企業の株式であるケースがあります。
通常、自社株式は事業の後継者に生前贈与等により移転させるものですが、企業経営に無関係の人が遺留分を主張して自社株を取得してしまうと、企業の意思決定に支障をきたす可能性があります。
たとえば、兄が事業後継者なのに、事業に無関係な妹が主要株主になってしまうと、円滑な意思決定ができません。
要するに、後継者以外の相続人に遺留分を主張されると困るわけです。
このため民法では、中小企業の後継者が経営者から生前贈与を受けた自社株式は、事前に遺留分権利者と合意したうえで経済産業大臣の確認を取り、家庭裁判所の許可を得れば、次のような特例を適用することが認められています。
- 除外合意・・・自社株を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度
- 固定合意・・・自社株の評価額を合意時の時価で固定できる制度

除外合意はなんとなく分かるが、固定合意の意味がよくわからんぞ
たとえば企業が利益を上げると、自社株の評価額も上がります。
自社株の評価額が上がるのは一見喜ばしいですが、それにより他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
また、後継者は相続財産に占める自社株の割合が高くなり、他の相続財産の取り分が少なくなってしまうかもしれません。
後継者にしてみれば、努力して自社株の評価を上げたのに損をするという矛盾が生じてしまうわけです。
それでは後継者がかわいそうなので、自社株の評価額を贈与時の時価で固定し、その後の値上がりを考慮しないようにするのが「固定合意」というわけです。
少し難解ですが、「中小事業主資産相談業務」を受験する方やFP1級まで狙っている方は、しっかり理解しておいてください。

遺留分に関する民法の特例は非上場企業が対象です。上場企業は対象外なので注意しましょう。
遺留分まとめ
ここでFP2級試験における遺留分のポイントをまとめておきます。
- 遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は1/3、それ以外の場合は1/2
- 代襲相続人は遺留分の対象、兄弟姉妹は遺留分の対象外
- 遺留分侵害額請求権では、金銭債権のみ請求できる
- 遺留分侵害額請求権は、相続開始を知った時から1年または相続開始から10年経過すると時効になる
- 家庭裁判所の許可により、相続開始前に遺留分を放棄できる
- 遺留分に関する民法の特例には、除外合意と固定合意がある

今回の講義はここまでです。3つの遺言と遺留分は確実に理解しておこう!次回は成年後見制度を解説していきます。


試験対策には“直前対策note(〜2026年5月試験対応)”がおすすめだぞ