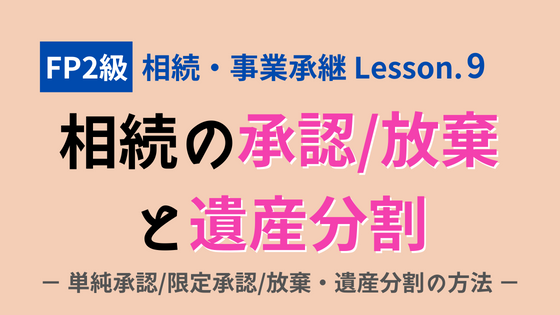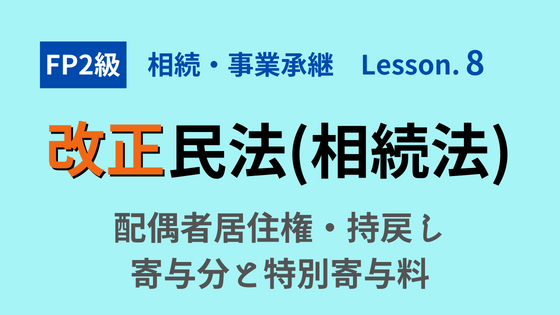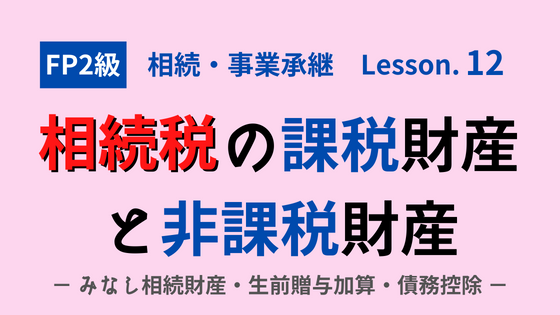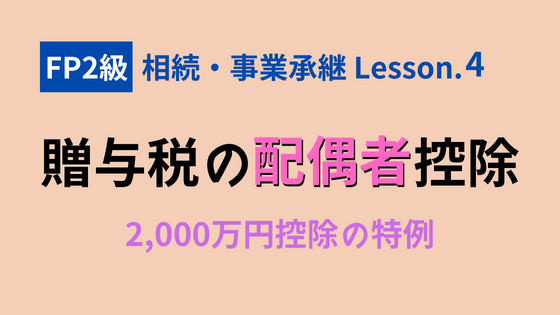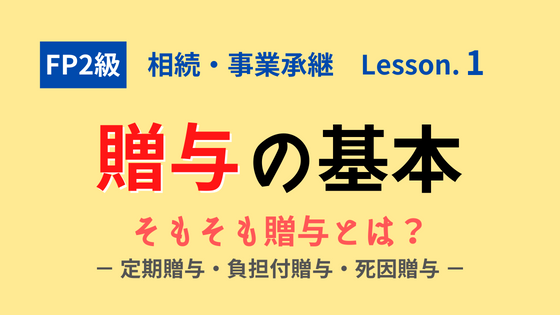【FP2級】贈与税の基本 〜贈与税額の計算と申告〜
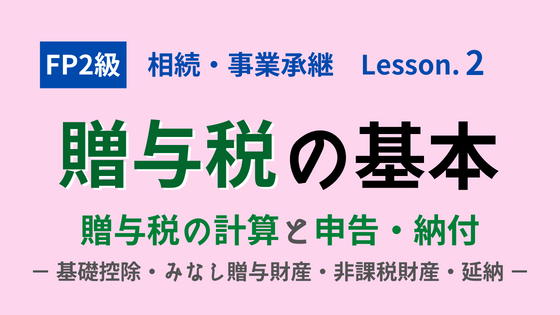

前回は「贈与」の基本を学習しましたが、今回のテーマは「贈与税」の基本です。”税”と聞くと難しそうですが、贈与税の難易度は低めです。確実に得点源にしていきましょう。
- 贈与税額の計算方法を理解する ←簡単です
- みなし贈与財産と非課税財産を理解する
- 贈与税の申告と延納を理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ
贈与税とは
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた人(受贈者)が納めなければならない税金です。
贈与を受けた財産の価値が大きいほど、贈与税の支払額も大きくなります。
贈与税は相続税を補完する役目を果たします。贈与税があることで、生前の財産移転により相続税を逃れようとする行為を防げるからです。
贈与税の課税の方法は「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つがありますが、今回解説するのは「暦年課税」の方です。
- 暦年課税(通常の贈与) ←今回はココ
- 相続時精算課税
なお、次の2つは贈与ではなく、相続税の課税対象になるので注意が必要です。
なんで7年以内だと相続税の対象になるんだ?

駆け込み贈与による相続税の節税を防ぐためです。この後学習する110万円の基礎控除内であれば贈与税はかかりません。亡くなる前に基礎控除を上手く使って節税することを防止しているわけですね。

贈与税額の計算
贈与税の計算式
暦年課税による贈与税の支払い金額は、次の式で計算されます。
FP2級以上では基本中の基本なので必ず覚えておきましょう。
「贈与税の課税価格」とは、1月1日〜12月31日までに受け取った財産の合計額です。
金銭だけでなく、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものの贈与は、贈与税の課税価格に算入されます。
そこから基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率を乗じて贈与税額を算出します。
税率は課税価格が大きいほど高くなり、最高税率は驚異の55%です(2024年度)。
みなし贈与財産と非課税財産
贈与税の課税価格には、みなし贈与財産は含みますが、非課税財産は含みません。

「みなし」ってなんだ?
“みなし贈与財産”とは、例えば次のようなものです。
| 保険金 | 保険料を負担した者以外が受け取った満期保険金 (例)父が保険料を負担した満期保険金を娘が受け取った |
| 債務免除 | 債務免除による利益を受けた場合 (例)1,000万円の借金をチャラにしてもらった |
| 低額譲渡 | 著しく低い価格で財産を譲り受けた場合 (例)2,000万円の土地を500万円で譲り受けた |

「みなし」を「実質的な」と言い換えると分かりやすいよ!
みなし贈与財産については、次のポイントをおさえておきましょう。
次に“非課税財産”とは、贈与税がかからない財産を指します。
例えば次のようなもので、国民感情や社会政策的な見地から、贈与による財産移転があっても贈与税は課されません。
- 法人から個人への贈与財産(所得税や住民税の対象)
- 親から子に対する教育費や仕送りなどの援助
- 香典、祝物、お見舞金
- 離婚による財産分与
- 特定障害者扶養信託契約に基づき、特定障害者が受け取る信託財産(上限6,000万円)
親から子への仕送りは非課税財産ですが、子供が生活費ではなく、例えば資産運用(株の購入など)に使ってしまうと、贈与税の課税対象になってしまうので注意が必要です。
親から子への贈与は以下の点を整理しておきましょう。
また、離婚による財産分与や香典・祝金・お見舞金であっても、社会通念上、明らかに高額な場合は贈与税の課税対象になる場合があります。

離婚の財産分与は非課税だけど、がっぽり貰い過ぎると課税されるわけだな
基礎控除110万円
贈与税の基礎控除は110万円です。
1年間で1,000万円の贈与を受けた人は、110万円を差し引いた890万円に対して贈与税がかかることになります。
一方で、1年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税はゼロで、申告も不要になります。
贈与税は、基礎控除以外にも一定の要件を満たすと様々な控除の特例を受けることができます。(贈与税の特例は、次の講義以降で解説していきます。)
税率と特例贈与財産
贈与税は、贈与を受けた金額が大きくなればなるほど税率が上がる「超過累進課税」です。
例えば、贈与を受けた額が200万円以下であれば税率は10%ですが、贈与を受けた額が3,000万円を超えると税率が55%にまで跳ね上がります。

ずいぶん高いんだな

相続税より税率が高くなるケースが多いから、贈与はよく考えから実施した方が良さそうだね
また「特例贈与財産」の場合は、一般贈与財産よりも税率が低く設定されています。
特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が直系尊属(両親や祖父母)から贈与を受けた財産のことです。
赤の他人から受けた贈与よりも、両親や祖父母から受けた贈与の方が、税制上優遇されているということですね。

FPの試験では税率表を暗記する必要はありません。問題用紙に税率表が書いてあるからね。計算のやり方だけ分かれば大丈夫!
ただし、最高税率が55%であることは押さえておこう。
贈与税の申告と納付
贈与税の申告
繰り返しになりますが、贈与を受けた金額が110万円以下で贈与税額がゼロの場合は、申告書を提出する必要はありません。
一方で、納付すべき贈与税がある場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に、贈与税の申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出先は、受贈者の居住地を管轄する税務署です。
贈与者の居住地ではないので、ひっかけ問題に気をつけましょう。
条件を満たせば「延納」もできる
贈与税は申告書の提出期限までに、金銭で一括納付するのが原則です。
一括納付ができない場合は、最長5年まで「延納」を選択することができます。
延納とは、税金を分割して納めることです。
ただし、延納を選択するには、次のような条件があります。
- 期限までに申告書を提出し、税務署長の許可を得ること
- 贈与税額が10万円を超えていること
- 担保を提供すること
※ただし、延納期間が3年以内かつ延納税額が100万円未満の場合は担保不要

ちなみに贈与税では物納は選択できないよ。物納が認められるのは相続税だけ。引っかけ問題で頻出だから注意しよう!
| 贈与税 | 延納は可、物納は不可 |
| 相続税 | 延納も物納も可 |
過去問チャレンジ
最後に、実際の過去問を解いてみましょう!
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
- 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
(2022年5月 FP2級学科)
それでは解説していきます。
❶不適切。
贈与税の申告期間は2月1日〜3月15日です。設問は、所得税の確定申告期間なので、しっかり区別しておくようにしましょう。
❷不適切。
申告書の提出先は、「受贈者」の居住地を管轄する税務署長になります。
❸不適切。
贈与税を納付するのは、「受贈者」です。
❹適切。
設問の通り、贈与税では5年まで延納が認められます。一方、贈与税では物納は認められていないことも、あわせて覚えておきましょう。
以上により、正解は❹です。

贈与税の基本は以上です。次回は相続時精算課税制度を学習します!
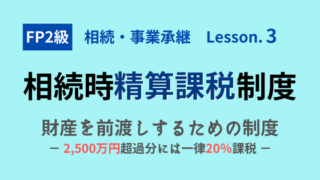

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ