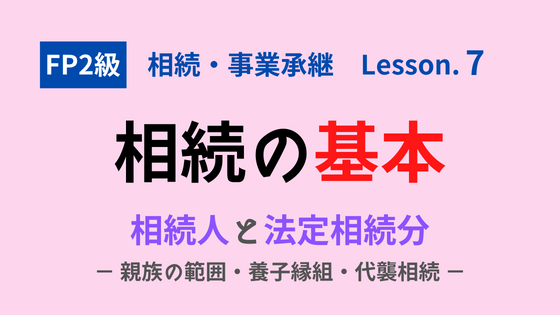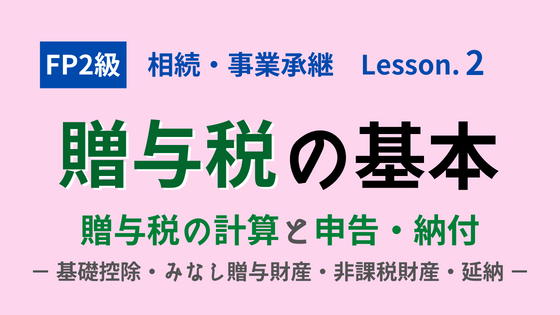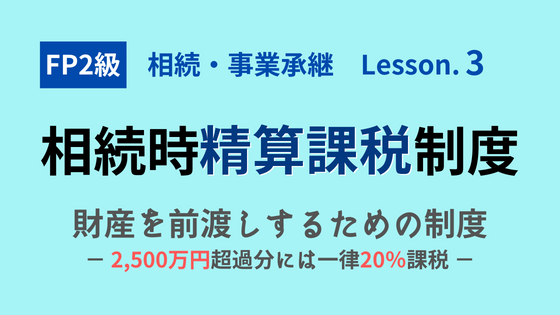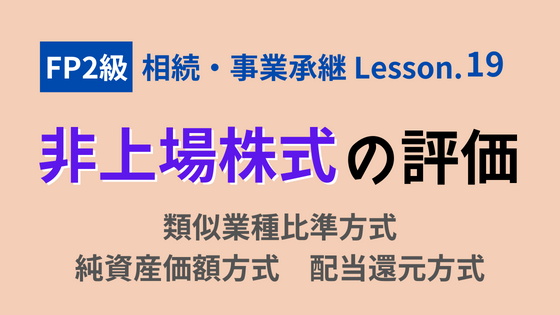【FP2級】改正民法(相続法)〜配偶者居住権・持戻し・寄与分と特別寄与料
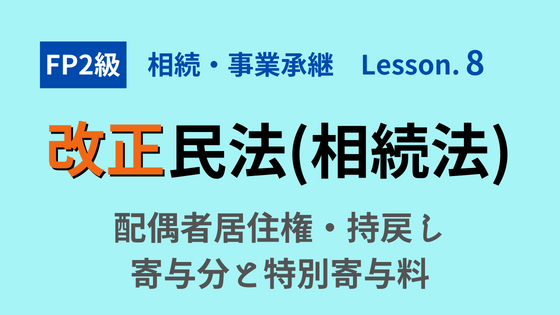

今回は配偶者居住権など、2018年改正民法(相続法)で新設された権利を中心に学習します。配偶者居住権と特別寄与料は特に重要です!
- 配偶者居住権を理解する
- 特別受益と持戻しを理解する
- 寄与分と特別寄与料を理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ
改正民法(相続法)のポイント
2018年7月に約40年ぶりとなる民法(相続法)の改正が行われました。
1980年から長らく改正されていなかった民法(相続法)ですが、現代社会に合わせて様々な点が改正されています。
では、具体的にはどのような点が改正されたのでしょうか。
まずはFP2級で出題される可能性が高いポイントを整理しておきましょう。
今回は上の3つについて学習していきます。
それ以外は別の講義で改めて解説しますね。
配偶者居住権
配偶者居住権とは
民法(相続法)改正の目玉が“配偶者居住権”の新設です。
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた自宅に配偶者が一生涯、無償で住み続けられる権利のことです。
具体的には、自宅の権利を「所有する権利」と「住む権利」に分け、配偶者は「住む権利」だけを相続することが可能になりました。

どうしてそんな権利が必要なんだ?
たとえば、夫所有の自宅に夫婦で居住していたとします。
夫が死亡すると、他の金銭資産と同様、自宅も遺産分割の対象になりますが、次のような問題が生じることがあります。
- 妻が自宅を相続すると他の金銭資産の取り分が少なくなり、生活に困窮する恐れがある
- 自宅を換金して遺産分割することもできるが、妻は生活の拠点を失ってしまう
配偶者居住権はこうした問題に対応し、配偶者の生活を守るための制度です。
配偶者は自宅の所有権を相続しないことで相続の取り分を抑えられるため、結果的に他の金銭資産を多く相続できるようになるわけです。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のイメージが湧くように、以下のケースを見てみましょう。
Bさんの夫Aさんが亡くなりました。Aさんの資産は自宅(評価額:2,000万円)と預貯金3,000万円です。BさんはこれまでAさん所有の自宅に同居していました。相続人はBさんと子のCさんです。
配偶者居住権を利用しない場合
このケースでは、相続人は配偶者と子なので、法定相続分は配偶者:1/2、子:1/2になりますね。
仮に法定相続分どおりに遺産分割をすると、取り分は2,500万円ずつになりますが、配偶者Bさんが評価額2,000万円の自宅の所有権を相続すると、預貯金は500万円しか相続できないことになります。
人生100年時代ですから、500万円だけでは老後の生活が苦しくなるかもしれません。
自宅を売却(換金)し、預貯金3,000万円と合わせてBさん・Cさんが按分することもできますが、この方法だとBさんは生活の拠点を失うことになります。
配偶者居住権を利用する場合
では、配偶者居住権を利用するとどうなるのでしょうか。
配偶者居住権を利用する場合、まず、自宅の権利を配偶者居住権と所有権に分割します。
仮に配偶者所有権と所有権の評価額は、どちらも1,500万円だったとします。
そのうえで、Bさんが自宅の配偶者居住権を、Cさんが所有権を取得すると、BさんとCさんは自宅の権利を1,500万円ずつ相続したことになります。
この場合、自宅の権利はBさんとCさんが均等に取得するわけですから、残りの預貯金2,000万円もBさんとCさんで均等に分割することになります。
結果的にBさんは配偶者居住権により生活の拠点を維持しつつ、預貯金1,000万円(2,000万円×1/2)も相続することができるというわけです。
配偶者居住権の留意点
配偶者居住権のメリットが分かったところで、以下の留意点を押さえておきましょう。
特に1つ目の「相続発生時に居住していること」という条件は重要です。
第三者に使用収益させる場合、建物の所有者の承諾が必要であることまで覚えたら完璧です。

“使用収益”は”賃貸”と読み替えると分かりやすいです。
持戻しと持戻し免除の意思表示
特別受益と持戻しとは
“特別受益”とは、被相続人から受けた贈与や遺贈のことを指します。
具体的には、被相続人から贈与を受けた学費や結婚資金、土地や建物の無償贈与などが挙げられます。
特別受益を受けた人のことを“特別受益者”、特別受益により取得した財産を”特別取得財産”と言います。
相続人の中に特別受益者がいる場合、実質的に特別受益者が得た財産が多くなり、他の相続人に対して不公平が生じてしまいます。
このため、被相続人の相続財産に特別受益財産を加え、これを除いた額を特別受益者の相続分とすることで相続人同士の不公平を解消します。
このように、特別受益財産を相続財産に加算して遺産分割することを“持戻し”といいます。
イメージが湧くように、次のケースを考えてみましょう。
被相続人である父の相続財産は4,000万円です。相続人は、妻・姉・妹の3人です。法定相続分に応じて遺産分割を行います。ただし、姉は父の生前、結婚資金として400万円の贈与を受けていました。
4,000万円を法定相続分に応じて分割すると、母2,000万円、姉1,000万円、妹1,000万円ずつ相続することになります。
しかし、姉は生前に400万円の特別利益を得ているため、これを持戻ししたうえで相続財産の計算を行うことになります。
つまり、相続財産はもともと4,400万円だったものとして計算します。
これを法定相続分に応じて再度計算すると、母2,200万円、姉1,100万円、妹1,100万円を相続することになりますね。
ただし、姉は既に受け取っている特別受益400万円があるため、相続における取り分は700万円(1,100万円ー400万円)になるというわけです。
持戻し免除の意思表示
原則として特別受益は持戻しの対象になりますが、被相続人が「持戻しをしなくてもOKだよ」と意思表示をしていれば、持戻しをしなくてもかまいません。
このような被相続人の意思表示のことを“持戻し免除の意思表示”といいます。
先ほどのケースにおいても、父が持戻し免除の意思表示をしていれば、姉は結婚資金の持戻しをする必要はないわけです。
持戻し免除の意思表示の推定
民法改正により、持戻しに関する新たなルールができました。
20年以上の婚姻関係にあった配偶者が、居住用建物や敷地を贈与や遺贈により取得した場合、「持戻し免除の意思表示」があったものと推定し、被相続人の意思表示がなくとも、持戻しの対象にはしないというルールです。
これを“持戻し免除の意思表示の推定”といいます。
配偶者居住権と同じように、配偶者の生活を守るためのルールです。
贈与を受けた自宅が持戻しの対象になってしまうと、配偶者は相続による取り分が減り、生活が困窮してしまうかもしれません。
「持戻し免除の意思表示の推定」により、配偶者は贈与を受けた自宅を別枠としたうえで、通常の遺産分割により金銭資産等を相続することができます。

婚姻関係20年以上の要件は、贈与税の配偶者控除と同じです。セットで押さえておこう!
寄与分と特別寄与料
寄与分
少し長くなってきましたが、もう少しなので頑張りましょう!
“寄与分”とは、事業の手伝いや療養看護など、被相続人に特別の寄与をした人に対して、相続財産の取り分をプラスする制度です。
たとえば、被相続人である父の事業を手伝ってきた長男や、長年父の介護をしてきた長女が、他の兄弟姉妹と同じ相続分では不公平ですよね。
こうした不公平を解消するために、特別の寄与をした相続人には寄与分を上乗せして、各相続人の相続分を計算します。
特別の寄与をした被相続人以外からの金銭請求(特別寄与料)
ここで問題となるのは、寄与分が認められるのはあくまで相続人だけだということです。
つまり、長男の妻(姑)がいくら献身的な介護をしたとしても、相続人ではないため寄与分の対象にはなりません。
しかしこれでは姑さんが報われませんよね。
こうした不公平を解消するために民法(相続法)が改正され、相続人ではない親族が介護など無償で特別の寄与をした場合には、相続人に金銭が請求できるようになりました。
これを“特別寄与料”といいます。
特別寄与料を受領した者(特別寄与者)は、遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
特別寄与料は、相続の開始を知った時から6か月以内に請求しなければならないことも、合わせて覚えておきましょう。
まとめ
最後に今回の講義の重要ポイントをまとめておきます。
■ 配偶者居住権
- 配偶者が一生涯、自宅に無償で居住できる権利
- 登記することで第三者に対抗できる
■ 持戻し
- 贈与で特別受益を得た者の相続分を減らす制度
- 配偶者への居住用不動産の贈与は持戻し対象外
■ 寄与分・特別寄与料
- 寄与分は相続人にしか認められない
- 相続人以外で特別の寄与をした者は特別寄与料を請求できる

今後出題が増える可能性が高い分野なので、しっかり内容を理解しておこう!次回は相続の承認・放棄と遺産分割について学習します!
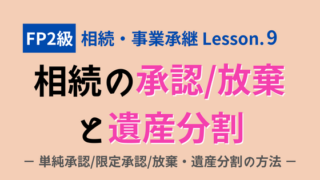

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ


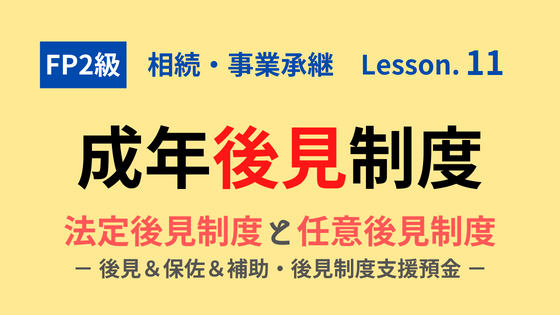
2.png)